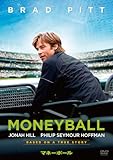元 DeNA 社員が明かすソーシャルゲームの秘密

Photo:Games By Ian D
ソーシャルゲームの世界は、いわゆるガラケーを主戦場として躍進してきた。スマホの時代になって、キャリア課金が難しくなれば、ソーシャルゲーム主体の会社は急落するかと思っていたが、コンプガチャが規制された後でも、その勢いに翳りは見られない。
そもそも、なぜソーシャルゲームで莫大な利益を出し続けられるのか?その疑問に答えてくれるのが、今回紹介する「ソーシャルゲームだけがなぜ儲かるのか」だ。著者は、ソーシャルゲーム会社大手の、DeNA の元社員の中山淳雄さん。
任天堂、ソニーらが減収する一方で業績絶好調の DeNA らソーシャルゲーム会社
本書によると DeNA は、七期連続の売上・営業利益の最高記録更新中で、11 年度決算は売上 1452 億円(対前年比 129 %)、営業利益 634 億円(他意前年比 113 %)、GREE も同様の伸びを見せているという。このデフレ不況のご時世に!
ゲーム業界と言えば、ファミコン、プレステ、Wii など、これまで多くのゲーム機が販売され、マリオシリーズやドラゴンクエストなど、数々のヒット作も生まれた。しかし、ゲームの世界はハードもソフトも開発には長い期間と多くの予算を投入する必要があり、当たれば天国、外せば地獄という感が否めない。そもそも、ゲーム業界自体が娯楽産業であり、衣食住満ち足りたあとに来るものという印象があり、不況の世の中で躍進するような業界とは考えにくい。
実際に「任天堂は、2008 年から減収が続いており、エンターテイメントを含めたソニーは、5200 億円の赤字」という状況。Wii が発売されたときには、これまでのコントローラを使ったゲームという概念が覆され、これからは任天堂の天下ではないかと思ったものだが、その状況は長くは続かなかった。
まさしく、本書のタイトル通り、「ソーシャルゲームだけがなぜ儲かるのか」という疑問が湧く。
ソーシャルゲームの収益性が高いのは、日本だけという事実

Photo:Japan – Kyoto By Marc Veraart
海外は、ARPU(Average Revenue Per User:ユーザー一人あたりのアイテムか金額) が 100 円にも満たない状態で、日本だけが収益性が高いという状況という。なぜ、日本だけなのか?日本のソーシャルゲームは、市場規模 3000 億円で、この 4 年間で毎年 4 倍ずつ成長してきており、世界でも、映画・雑誌・音楽などのエンタメ業界と比べて、ゲームだけが大きく成長しているのだそうだ。
この 3000 億円という市場規模は、世界のソーシャルゲーム市場 6500 億円のうちの約半分にもなり、これは、シャンプーの市場とほぼ同規模という。
日本のソーシャルゲームの成功要因
日本のソーシャルゲームが成功した要因には、「人を集める力」「人を熱狂させる力」「熱狂をお金に変える力」があり、さらにそれを実現した土壌として、次の 3 つのイノベーションがあったという。
「インフラ」
コンテンツによるキャリア課金システムやインターネット接続など、日本の携帯産業は世界を 10 年先取りしていた
「マーケティング」
人のスキマ時間を奪うイノベーション、リアルタイムマーケティング(ゲームをどんな風にチューニングすれば顧客を増やせるかを常に考え続ける)
「ソーシャル」
ソーシャルそのものは、古くからあるものだが、それをデジタル空間で再現したノウハウ
日本の携帯市場は、「ガラパゴス」などと揶揄されるが、他の国では白黒液晶しかなかったような時代に、携帯からインターネットにつなげており、キャリア課金という料金回収システムもできあがっていた。
これら 3 つのイノベーションの中で、私がもっとも印象に残ったのは、「リアルタイムマーケティング」というマーケティングのイノベーション。著者は、「遠隔操作で味が変わる飴玉」と表現する。従来のコンソール市場のゲームであれば、基本的には作ったらあとは販売するのみだが、ソーシャルゲームは、リリースしてからが勝負なのだ。
つまり、ゲームをリリースした後、ユーザー動向をリアルタイムに解析し続け、より多くのユーザーから課金できるようにゲームを最適化し続けるのだ。飴玉の味がリンゴだったとしても、解析の結果、ユーザーがオレンジを好むことがわかれば、その味を変更する(できる)のである。
ここで必要となるのは、莫大な量のデータを解析する能力。DeNA では、2011 年新卒入社 44 名のうち、東大卒が 19 名、京大卒が 6 名という。ゲームをチューニングする「情報解析のノウハウ」こそが、ソーシャルゲームの収益源になっているからである。
昨年、マネーボールという映画を見た。この映画は、有力選手を雇えない弱小球団が、従来型の直感的なスカウトを廃し、野球界を知らない、高学歴の若い担当者による、徹底的なデータ解析により、今後伸びていく可能性が高いが、スカウトの評価が低い選手を安く獲得し、チームの躍進に貢献するというストーリーである。ソーシャルゲームのマネタイズにも、これに近い論理性を感じる。躍進を支える根本は、運や直感ではないのだ。
| マネーボール [DVD] | ||||
|
DeNA は 2012 年には、新卒でも能力があれば、年収 1000 万という破格の待遇を提示した。高度な情報解析を行う頭脳には、それだけの価値があるということだ。一度ヒットを出せば、チューニングのノウハウがわかるため、モチーフを変えて売れるゲームを量産すれば、次のヒットを出す可能性も高くなるのだという。さらに、ゲームそのものをコピーされたとしても、裏側でパラメータをいじりながら最適値を探すノウハウは模倣できないため、海賊版にも強いのだ。
Facebook のような大衆性とパチンコのような高い投資性を兼ね備えるために、規制の難しさもあるという。確かに、いまやソーシャルゲームは、自分がやっていないとしても、まわりの人間をあたれば、誰かは遊んだ経験を持っているだろう。そんなユーザーの中から、月に 50 万という大金を投入するユーザーも出てくるのである。
ソーシャルゲームの成功に学び、新しい価値を創出していこう!!
農業などの生産者は「第一次産業」、製造業は「第二次産業」、そして、サービス業は「第三次産業」と呼ばれてきた。しかし、すでに就業者の七割が第三次産業に従事する現在、著者は、「情報」を第四次、「コミュニティ(関係性)」を第五次の産業として定義し、ビジネス創出のヒントについて最後の章で語っている。
終身雇用が過去のものとなりつつあり、銀行や自治体までもが破綻する時代において、安定を求めることは困難になってきている。だからこそ、企業に勤めていようとも、個人が考えることを止めるべきではない。自分の身を守るのは、自分なのだ。
私自身、今は会社勤めの身ではあるが、決して安泰とは思っていない。少子高齢化社会ではあるが、若く優秀な人材はどんどんと現れてくるし、近い将来、外国人比率も増えていくだろう。私はもうすぐ 41 歳だが、自分にはどれだけの価値があるのか、会社から投げ出されたときにどのような価値が提供できるのか、そんなことを強い危機感を持って日々考えている。
最近、BASE や、STORES.JP などネットショップを支援する新しいサービスが生まれている。ある程度の資本が必要とされていたサービスへの参入障壁が下がり、アイデア次第で、少人数で利益を出せる可能性が広がっている。
これらサービスの不安な面を上げれば、きりがないだろう。無謀になってはダメだが、幾つになっても、新しいものに挑戦していく意欲はなくさずに進んでいこうと思う。この本を読んで、そんな気持ちがさらに強くなった。
本書は、ソーシャルゲームのマネタイズの仕組みを知りたいという知的好奇心を満たすだけではなく、新しいビジネスへの取り組みのヒントにもなる良書だ。繰り返し読んで、ノウハウを吸収して行きたいと思う。
| ソーシャルゲームだけがなぜ儲かるのか (PHPビジネス新書)[Kindle版] | ||||
|